去年の夏頃にクラファンし、到着は1/17。一ヶ月ぐらいちょくちょく触っていたので使用感をまとめます。
まいにゅーぎあ pic.twitter.com/XH1CciNIt9
— Ka-Ka (@ka_ka_xyz) 2024年1月17日
まとめ
- 視力補正は動いている(感動的)
- でも視野は狭い
- 現状だと実用性よりも将来性や新しい体験を求める人向け
- 次世代機に期待
そもそもViXion01とは
“見える”を引き出す、取り戻す。
自動でピントを調節するオートフォーカスアイウェア。
眼の酷使や加齢にともなう⾒え⽅の課題解決をサポートします。
眼鏡と違い、対象物との距離を測定して動的に視力補正を行うデバイスです。
一応
※本製品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律における医療機器ではありません。
という点は認識した上で使用してください。また、下記ページの禁止事項や注意事項も把握してください。
自分の視力について
両目ともに視力0.1以下の近視+乱視。老眼は来てない状態です。日常生活で常時眼鏡装着。
Vixion01は乱視の補正は出来ないので、乱視が使用感を低くする方向に影響している可能性があります。また、動作原理として「近視+老眼」の組み合わせでも上手く補正できるはずですが、試すことが出来ていません。
見え方について
ViXion01を触ったことが無い人向けの説明として。
とりあえず、「指メガネ」を作りましょう。

画像はMS Copilotで生成。
で、指メガネを目から数センチ離して見てください。視野の中にぼんやりした輪っかが浮かんで見える状態になると思います。Vision01を装着したときの視野は基本これです。「視野の周辺にぼんやりした輪っかが浮かんで見えていて、その輪っかの内側部分だけはっきりと見える」状態。
おそらく、将来的にはレンズのサイズが大きくなり、「輪っか」は見えなくなっていくのだろうなと思いますが、現行のVixion01では使用中の視野には常に「輪っか」がついて回ります。
そのうえで、視力補正そのものはかなり良い感じ。対象との距離に合わせて自然にフォーカスを当ててくれる様子を体験すると結構感動的です。また、フォーカスを変える際の時間差や動作音もほぼ気になりません。遠くを見ているときにいきなり測距部に手のひらを当てるようなことをすれば流石にフォーカスが「動いている」様子がわかりますが、逆にそういうことをしなければ「動いている」事自体が意識出来ないレベル。
読書向けとしてどうか?
ViXion01はレンズ部が目の真正面に来るように左右位置調整を行う必要がありますが、近くを見るときには寄り目がちになるので位置調整をやり直す必要があります(「輪っか」が二重に見えてくる)。
仕事が引けたのでViXion01をもうちょっと触ってみる。
— Ka-Ka (@ka_ka_xyz) 2024年1月17日
うーん。読書用には微妙な感じがあるな。
視野が狭いことに加えて、レンズの左右位置調整は1m先を見て行うのだけれど、本を読むときには距離が20cmぐらいになるので、ちょっとより目になるのだな。
なので左右位置調整をやり直す必要がある。 https://t.co/eqM5h4QFTo
うーん。読書用には微妙な感じがあるな。
視野が狭いことに加えて、レンズの左右位置調整は1m先を見て行うのだけれど、本を読むときには距離が20cmぐらいになるので、ちょっとより目になるのだな。
なので左右位置調整をやり直す必要がある。
使えなくはないもののメガネに対する優位点は微妙という印象です。
PC作業用としてどうか?
裸眼だとほぼ見ることが無理なPCディスプレイでもViXion01を使えばはっきりと見えます。
ただ、視野の広さに問題あり
50cmぐらいの距離を置いて24インチのディスプレイ(幅53cm、高さ30cm)をみた時、カバーされる領域はだいたい
— Ka-Ka (@ka_ka_xyz) 2024年1月18日
- 縦は100%
- 横は60%
ぐらい。カバーされない領域を見る時には首を動かさないといけない。
50cmぐらいの距離を置いて24インチのディスプレイ(幅53cm、高さ30cm)をみた時、カバーされる領域はだいたい
- 縦は100%
- 横は60%
ぐらい。カバーされない領域を見る時には首を動かさないといけない。
ディスプレイが「輪っか」内の視力補正されている領域に収まらないため、頻繁に視線を動かす必要があります。で、眼球だけを動かすと「輪っか」から視線が外れるので、頭全体を動かす必要あり。
確かに視力補正は上手く動いているものの、「メガネの代わり」としては厳しいという感じです。ただし、将来的に「輪っか」がより大きくなった製品が出るとしたら、メガネ以上に使えそうな感触はあります。
もしかしたら疲れ目になりにくい可能性はありますが、それよりも「視野の中につねに輪っかが浮いている」状態のストレスのほうが強いです。一時間ぐらいで装着限界。
細かな作業等はどう?
遠視や老眼持ちであればこのあたりを評価できそうですが、現状だとなんとも言えません(あと、模型等の趣味も持っていないので)。ただ、ルーペとかを使ったほうが楽なのではないかなという気はします。
結論
初日の第一印象通り、「動的な視力補正技術という将来性への投資」あるいは「動的な視力補正技術への体験料金」という面でクラファン分の代金は十分回収できていると思います。
まだスマホアプリで設定を追い込んで無くて、本体側の調整だけでさくっと使ってみた段階だけれど、ちゃんと動的にピント合わせができている。
— Ka-Ka (@ka_ka_xyz) 2024年1月17日
ただまあ、視野が狭いのはなんともなあ。
いまのところ「"メガネの代わり"は無理。それはそれとしてクラファン品としては十分以上に面白いのでアリ」な印象
もともと動的な焦点補正という方向の将来性を買ったのであって、ViXion01という製品自体の実用性はあんまり期待していなかったので、まあよしというか。
— Ka-Ka (@ka_ka_xyz) 2024年1月17日
02(あるいは03あたり)が出たらまた買うと思うな。
ただ、時間ができたらもうちょっと設定を追い込んでみる。多分まだ潜在能力を引き出せて無い
一方で、室内での利用だけに限定したとしても、眼鏡の代替としては現状は不十分だと思います。なので、「メガネやコンタクトレンズと比較した場合のコスパ」的なモノを求めるならば、おすすめしません。
とはいえ、視野の狭さ(というか「輪っか」問題)が解決した次世代機が出るとしたら、完全代替えは無理としても、視力補正の新しい選択肢としてとても良いものになると思います。ということで次世代機開発計画を早く出して欲しい……


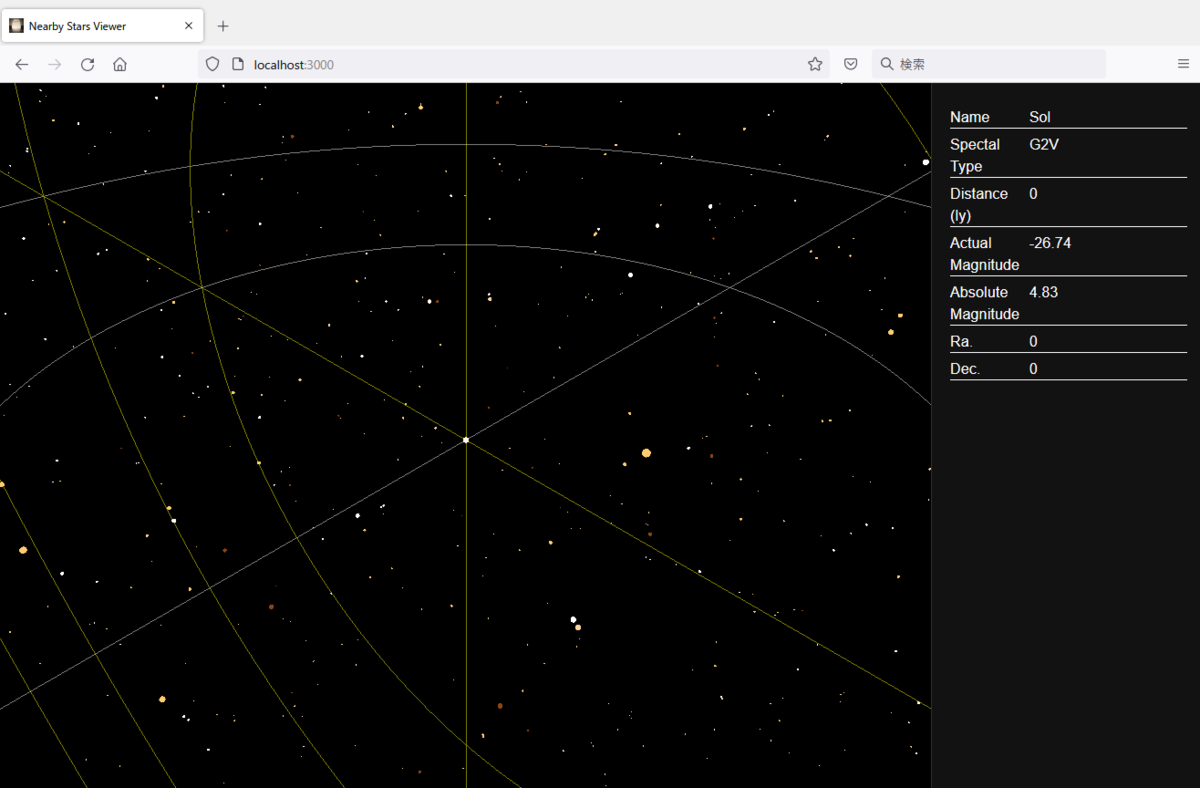
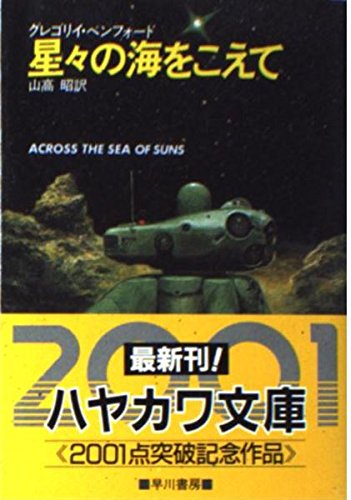
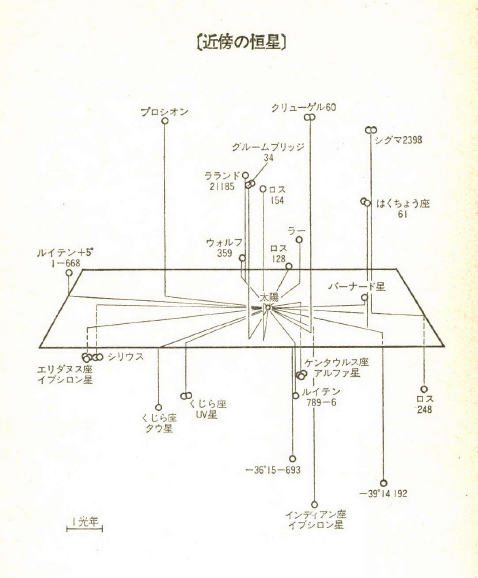
![終わりなき索敵〈上〉 [航空宇宙軍史] (ハヤカワ文庫JA 569) 終わりなき索敵〈上〉 [航空宇宙軍史] (ハヤカワ文庫JA 569)](https://m.media-amazon.com/images/I/51QG60GCQQL._SL500_.jpg)


